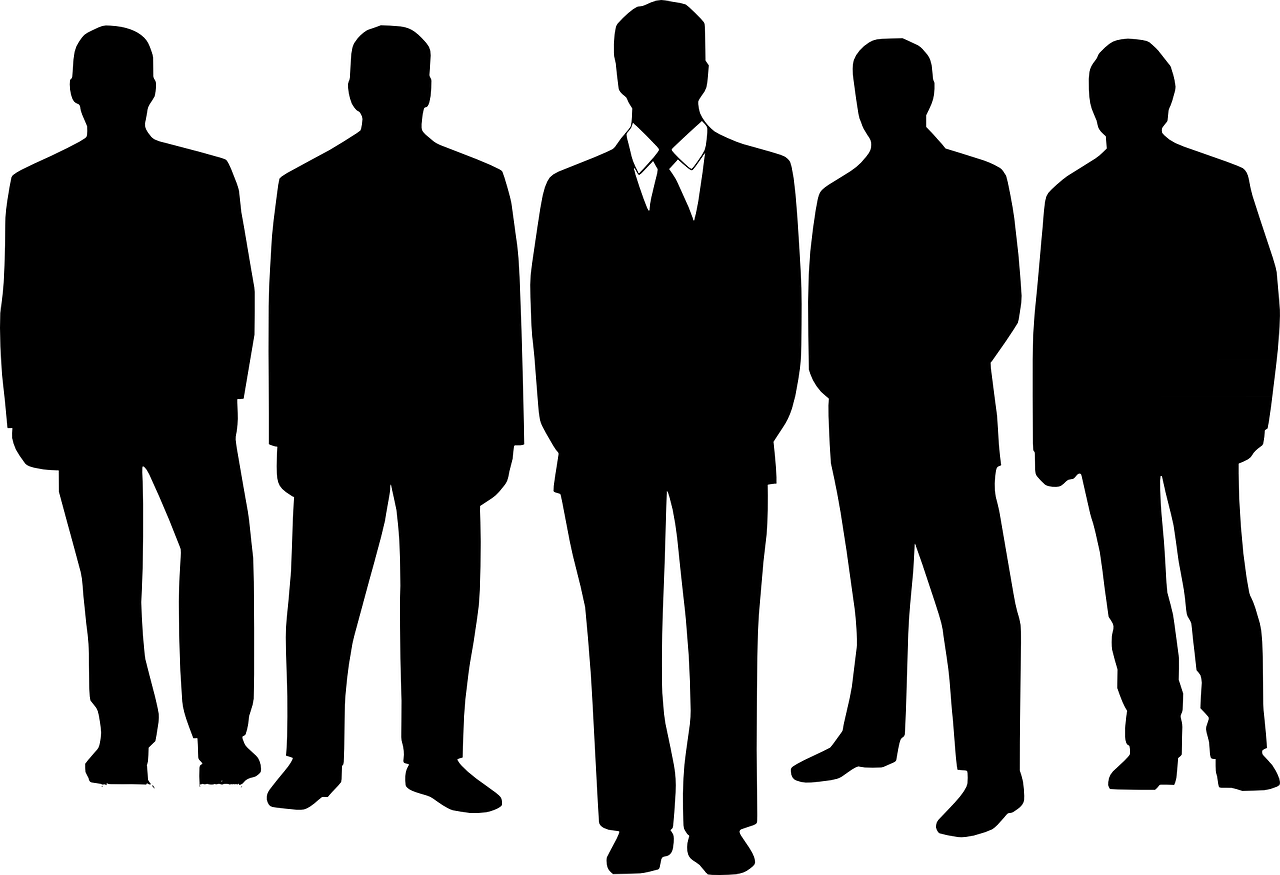研修医のための脳外科病棟カンファ14回目,2018年11月22日

11月20日(火曜日)は用時がはいり,22(木)に変更.
これは,研修医の先生向けとは言いつつ,実際は,自分の症例をまとめているだけのものですがカンファレンスの形を取って,とりあえず地域医療研修にきてくれた研修医師に,脳外科病棟に入院している患者さんの紹介をしているもの.
本日の症例1 70才代 常染色体優性多発嚢胞腎
脳動脈瘤破裂
自分は,初めて経験した.専門医の試験の時に出たような.
それは,「脳動脈瘤を合併しやすい疾患はどれか」と言う質問.
数年前に,腎機能が正常なときに未破裂中大脳動脈瘤の開頭ネッククリッピングをしていた.その人がまたくも膜下出血で運ばれてきた.
採血では腎機能障害が進んでいる.CTAは出来ないとみていると,
お腹のCTを以前撮っていた.それで答えは判明.
ADPCK(常染色体優性多発嚢胞腎症)で,特定疾患の人である.
自分が来る前に,他の医師がクリッピングをしている.
この疾患のヒトは2-4%が脳動脈瘤破裂で死亡する.
脳動脈瘤も「腎機能が正常なうちに50%は破裂する.」ので,
見つかれば手術が正しい.
数年前は,確かに腎機能は境界線であった.
この時,偶然,救急外来にいた別の先生が,
「腎臓に嚢胞がたくさんできたら,脳動脈瘤ができるんですか」と
一般人なら,そう思うのも無理はない質問をしてきた.
要は,腎機能が低下して腎臓由来の高血圧となり,
それで動脈瘤ができるのかという質問.
このケースは,染色体異常の疾患であり,
質問は原因と結果が逆である.
「多発嚢胞腎にもなるし,脳動脈瘤も出来る」のが答え.
まあ,夜に運ばれて重度の腎不全でくも膜下出血もあってとなると,
自分の病院では,手に余る.
治療法は,以前のクリップの部分から拡張した場所に,
コイルをつめることになると予想しましたが
転院先からの連絡はなしです.
本日の症例2 70才代 血管周囲腔の拡大
頭位変換性めまい,後頭部の筋肉痛と症状は,ありふれたもの.
CTを撮ると,右基底核の下外部分に1.5 cmの大きな嚢胞があるというので,紹介された.
CTもきれいで,髄液と同じ黒さ.境界もきれいである.
MRIを撮ってみて,判明.
予測通りでしたが,1.5cmのスペースの中に血管が走行しているのが,わかる.
T2でわかる.
出来やすいというか起きやすい場所は,基底核の下1/3程度の場所とか海馬とか,
大きな物は1 cmになると書いてあるが,これは1.5 cm.
自分の解釈がただしければ,血管周囲腔の拡大である.
Virchow-Robin 腔の拡大である.
日本語では,ウィルヒョウ ロビン腔であるが,
英語圏ではバーコー ロバンと発音していたと記憶している.
先天的なもの.3 mm程度なら結構みるが,
70才代になって何も症状を出していないので,造影したりもしなかった.
本日の症例3 10才代 外傷性脳脊髄液減少症
スポーツをして,背中から落ちて,
4日目ぐらいから,起きたら頭痛,横になったら改善
3週間もすでに学校を休んでいる.
自分の特殊な検査でも,初圧も低くなく,なんとも言えない.
ということで,そのまま硬膜外自己血注入をするのは,なかなか大変である.
そこで,硬膜外に持続生食注入をしてみようと思ったが,
まずは,専門病院に紹介して,みてもらい,してもらう.
その具体的な方法と考え方,全体のシステムを見学に行った.
そのノウハウは,研修医の先生には不必要な知識と技術である.
患者さんが良くなって帰ってくることを祈っています.